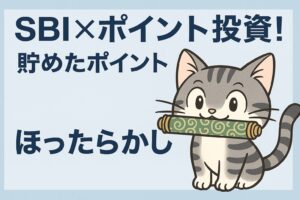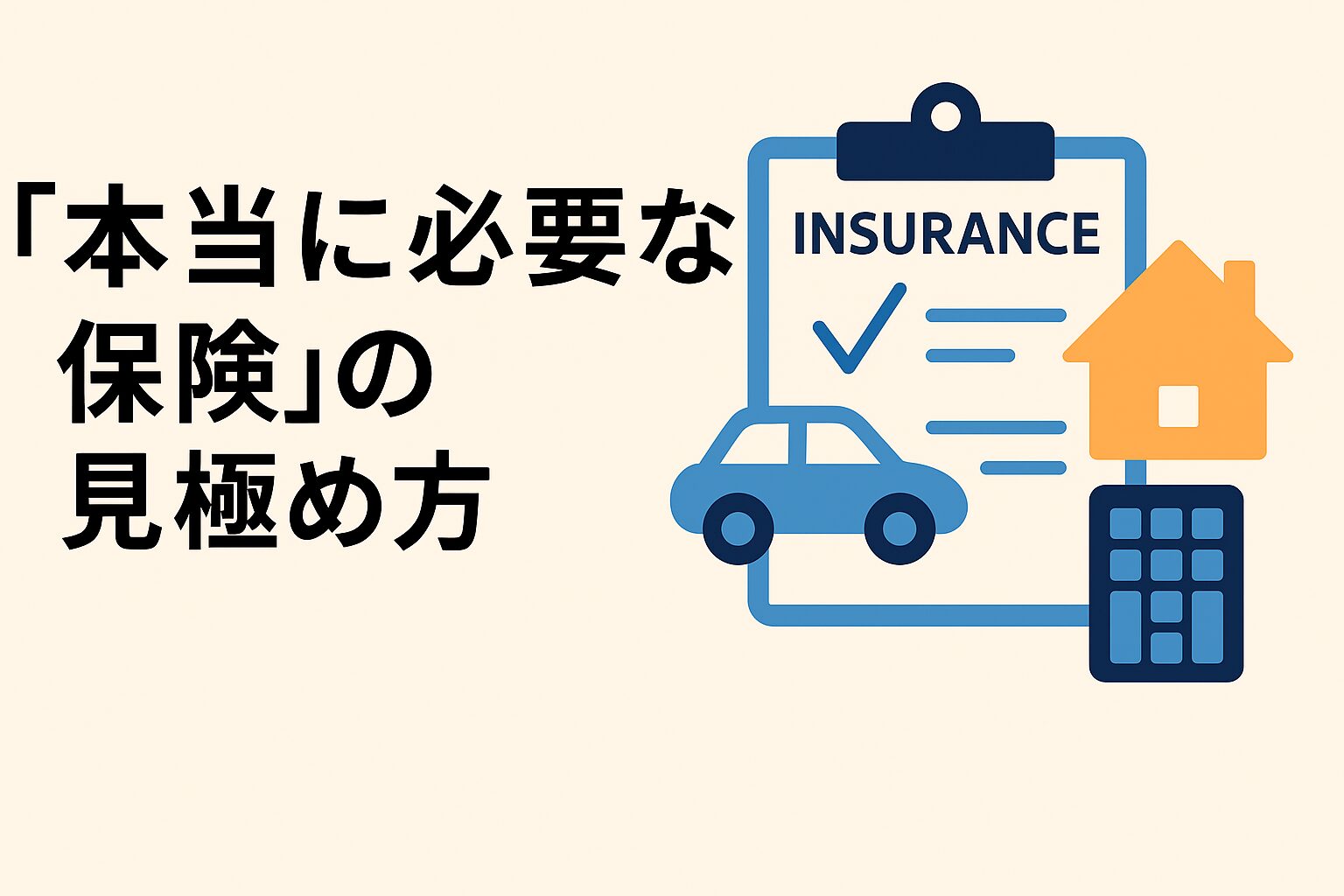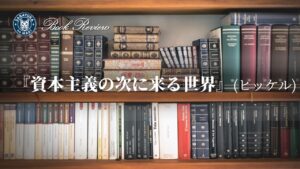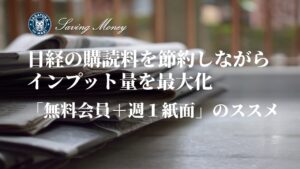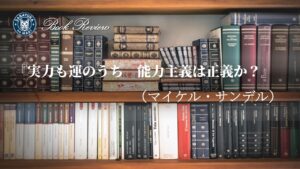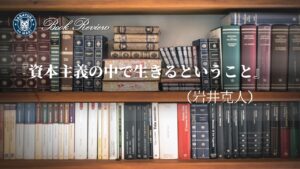「そもそも保険って入ったほうがいいの?」
「どの保障を選べばいいか、さっぱり分からない」
このように思っている方は、数多くいます。
保険は種類が多く、仕組みも複雑。専門用語もずらりと並び、比較するのも一苦労。中には、保険会社が“あえて分かりにくく設計しているのでは?”と思ってしまうような商品もあるのが現実です。
この記事では、大手金融機関で商品開発の経験を持つファイナンシャルプランナーである管理人が、「本当に必要な保険」をどう見極めればよいのか、その判断軸をできるだけわかりやすく、シンプルにお伝えします。
この記事を読めば、保険会社や営業トークに振り回されることなく、あなた自身の判断軸で「本当に必要な保険」を選べるようになります。
保険選びのよくある間違い
保険を選ぶとき、ついやってしまいがちな間違いがあります。それは——
「この保険に入ったら得かどうか?」(損得勘定)で判断してしまうこと。
たとえば、支払う保険料に対して、どれだけ保険金を受け取れるか。「元が取れるかどうか」を気にしてしまうのは、よくあることです。でも、これは保険の本来の役割とはズレてしまっています。
スマホ保証の例で考えてみる
あなたがスマホを買いにお店へ行ったとします。店員さんから、こんな説明を受けました。
「このスマホには1年間の基本保証がついていますが、追加で5,000円払えば、保証を3年間に延長できますよ」
このとき、多くの人はこう考えるはずです。
「修理代が3万円かかることもあるし、5,000円なら入っておいた方が得かも?」
つまり、「壊れたときに得するかどうか」で判断します。
でも、私たちはそのスマホが2年以内に壊れる確率を正確に予測できるでしょうか?
また、修理代は本当に3万円なのでしょうか?
保険会社は、これらを正確に計算した上で、利益が出るように保険料を決めています。加入者全体で見れば「保険金を受け取る人」より「何も受け取らない人」の方が圧倒的に多いのです。
さらに、よくある故障(落下や水没など)は「免責事項」として保証の対象外になっていることも多く、私たちがイメージする“もしもの備え”は、実はカバーされていないことさえあります。
保険に加入すべきかを見極める方法
結論から言うと、保険の必要性は——
「そのリスクを、自分で許容できるかどうか」で判断することができます。
もう少し噛み砕いて言えば、
そのリスクが現実に起こったとき、出費をしても生活が破綻しないかどうか。
- 許容できないリスク → 保険で備える
- 許容できるリスク → 保険は不要
この“リスク許容度”は、人によって異なります。
たとえば同じ資産1,000万円を持っていても、
- 独身で支出が少ない人 → 許容度は高い
- 子育て中の家庭 → 許容度は低い
また、収入の安定性も影響します。
- 会社員で安定収入がある →許容度は高い
- フリーランスや自営業 →許容度は低い
自動車保険の例で考えてみる
たとえば、あなたが新車を購入して、週末のドライブを楽しみにしているとします。
でも、交通事故のニュースや教習所の教材を見ると、運転にはリスクが伴うことを改めて実感するはずです。こうした中で、多くの人は自動車保険(任意保険)に加入します。
ではなぜほとんどの人が入るのか?
「事故が頻繁に起きるから」ではありません。
一度でも起きたときの損害が、あまりに大きすぎるからです。
交通事故で人を死なせてしまった
→億単位の損害賠償が発生する可能性
このようなリスクは、ほとんどの人が自腹で負えるものではありません。だからこそ、自動車保険は「入って当然」とされるのです。
これは「得か損か」で考える話ではなく、“人生を破壊しかねないリスク”に備える合理的な判断です。
逆に言えば、「起きても自分で対応できるリスク」なら、保険に頼る必要はありません。
保険の本来的な機能とは?
「保険はリスクを許容できるかどうかで判断する」という話をしました。
では、そもそも、なぜ保険という仕組みが存在するのでしょうか?
その原点をたどると、保険が本来もっている“機能”や、選び方の本質が見えてきます。
保険の本質は「相互扶助」
保険の始まりは、仲間同士が助け合う仕組み。
古くは商人や船乗りたちが、ある仲間が損害を受けたときのために、あらかじめお金を出し合い、いざというときにその資金で支え合う仕組みを作りました——これが相互扶助の考え方です。
つまり保険とは、リスクを分散し、みんなで“もしも”を乗り越える仕組み。個人では背負えないような損失を、社会全体で肩代わりする装置なのです。
記録に残る最古の保険制度は、14世紀のイタリア・ジェノヴァで始まったとされる海上保険です。
当時の地中海では、海賊や嵐で船や積荷が失われることが頻発していました。そこで、複数の出資者がリスクを分担し、もし船が沈んだ場合には、事前に集めた資金から損失を補填する仕組みがつくられました。これが保険の原型です。
その後、火災保険、生命保険などへと発展し、社会に必要不可欠な制度となりました。
リスク許容度という視点は、保険の原点
保険とはもともと、個人では背負えないようなリスクに備えるためのもの。
だからこそ、「そのリスクを、自分で許容できるかどうか」という判断軸で保険選びをすることは、保険の原点にある相互扶助の考え方とも整合的です。
つまり、本当に必要な保険とは——
「人生が大きく揺らぐリスク」に備える保険。
それ以外のリスクは、自分の貯蓄や備えで対応する。これが、保険の“本来的な使い方”です。
なぜ保険選びは難しくなったのか?
保険は本来、「個人では背負えないリスクを、社会全体で支える仕組み」です。
にもかかわらず、現代では、
「どの保険に入ればいいのか分からない」
「保険が必要かどうか、自分で判断できない」
といった声が絶えません。
その背景には、保険業界に根づく“構造的な問題”があります。
問題は「リスクの過剰演出」
たしかに、現代社会にはさまざまな“新しい不安”が登場しています。
- 高額な先進医療費
- サイバー攻撃や個人情報の流出リスク
- 自然災害、感染症、そして孤独死…
こうしたリスクに応じて、保険会社は新商品を次々と投入します。
ですが実際には、少なくとも個人単位で言えば、「本当に保険で備えるべきリスク」自体は、昔とそれほど変わっていません。
多くの保険会社や販売現場では、本来であれば「自分で対応できる範囲のリスク」まで、まるで人生を左右するような不安として訴えるインセンティブが働いています。なぜそんなことが起こるのか。それは、保険業界の構造そのものに理由があります。
- 保険会社は、新商品を増やして売り上げを伸ばしたい
- 代理店や営業担当者は、契約件数によって報酬が決まる
この仕組みのなかでは、たとえ本当は必要ない保険でも、「必要に見せかけて売る」動機が働いてしまうのです。実際、高齢者への不適切販売などが社会問題となり、金融庁も保険会社への監督を強化しています。
ここで、もう一度立ち返りたいのは——
保険そのものは決して不要ではないということ。
ただし、必要なのは「リスク許容度を超える、本当に備えるべきリスク」に対応する保険です。
保険加入を判断するためのステップ
これまで紹介してきたように、保険に入るべきかどうかは、「そのリスクを、自分で許容できるかどうか」で判断できます。
この判断を行うには、次の2ステップが有効です。
「いくらまでの出費なら、自分で対応できるか」を考えます。このリスク許容度は、人によって大きく異なります。
判断ポイントは、主に以下の3つ:
- 資産額(特に流動性のあるもの)
現金、預金、株式、投資信託など、すぐに使えるお金が多ければリスク許容度は高くなります。 - 家庭状況(支出の多さ)
同じ資産でも、独身なら使えるお金が多く、子育て中の家庭なら制約が増えます。 - 収入の安定性
会社員のように安定した収入がある人と、フリーランスや自営業のように収入が不安定な人では、備える必要があるリスクも変わってきます。
たとえば…
- 独身で資産1,000万円 → リスク許容度は高い
- 子どもが2人いる家庭で資産1,000万円 → 教育費などがかさみ、実際に使える余裕資金は限られる
このように、自分にとって「どれくらいの損失までなら生活を維持できるか?」を把握することが、判断の出発点です。
次に考えるのは、その保険でカバーしようとしているリスクが、どれだけ大きいかです。これも保険の種類によって、想定される損失額が大きく異なります。
リスク金額の目安(例):
- 車の破損(車両保険):100万〜200万円
- 死亡保障(子どもが成人するまでの生活費):2,000万〜3,000万円
- がん治療の費用(先進医療込み):数十万〜300万円程度
- 自動車事故で人を死なせてしまった場合:数千万円〜1億円
自動車保険や火災保険など「モノを守る損害保険」は、比較的リスクの金額が明確です。
一方で、生命保険や医療保険の“必要保障額”は、少し注意が必要です。
生命保険の必要保障額
生命保険の役割は、万が一のときに、遺された家族の生活を支えるお金を残すことです。
つまり、死亡した場合に備えて、「家族が生活していくために必要なお金=必要保障額」をカバーするように保険金額を設定します。
必要保障額の目安
もっとも一般的なのは、子どもが成人するまでの生活費+教育費。たとえば、小さなお子さんがいる家庭では、2,000万〜3,000万円前後が一つの目安となることもあります。
ただし、これはあくまで一例。家庭の状況によって変わってきます。
- 配偶者が働いているか?
- 持ち家か賃貸か?
- 教育方針(私立/公立)や、老後の備えは必要か? など
自分でシミュレーションをするのが難しい場合は、プロのFPに相談して必要保障額を算出してもらいましょう。プロに無料で相談できるサービスもあります。
プロの無料相談はこちら
リクルートが運営する「保険チャンネル」
医療保険の必要保障額
医療保険は、病気やケガによる入院・手術などの医療費に備える保険です。
ただし、ここで一つ重要なのが、日本の公的医療保険制度の存在です。日本では、全員が「健康保険」や「国民健康保険」に加入しています。この公的制度のおかげで、医療費の自己負担は原則3割に抑えられています。
さらに、「高額療養費制度」によって、月額の自己負担に上限があるため、たとえば100万円の治療費がかかっても、実際の負担は数万円〜十数万円で済むことが多いのです。
このように、すでに手厚い公的保障があるなかで、民間の医療保険に入るというのは、追加の保険に入ること=二重加入になります。そのため、「医療保険は不要」という考え方も存在します。
もちろん、すべての人に不要というわけではなく、貯蓄に自信がない、先進医療やがん治療への備えをしたいといった場合は、補完的な役割として医療保険を活用するのも選択肢です。
保険の無料相談はこちら
ケーススタディで判断してみる
ここからは、具体的な事例をいくつか取り上げて、「保険に入るべきかどうか?」をリスク許容度の視点から判断してみます。
繰り返しになりますが、人によって資産状況や家族構成は異なるため、これはあくまで“考え方のプロセス”として参考にしてください。
- 流動性のある金融資産:1,000万円
- そのうち700万円は「万一のために使ってもいい」と考えている
- 夫婦+子ども1人(小学生)で、30代の会社員
①スマホの延長保証(保証料5,000円、2年間追加保証)
- 加入しない。
(理由)万が一の修理費が3万円〜5万円程度と予想され、700万円のリスク許容枠の中で十分に対応可能。生活が破綻するリスクとは言えない。
②自動車保険(保険料年2万円、対人・対物無制限)
- 加入する。
(理由)事故によって他人を死亡・重傷させた場合、数千万円〜1億円規模の損害賠償が発生する可能性がある。これは明確に“許容できないリスク”。
③自動車の車両保険(保険料年3万円、車両補償200万円まで)
- 加入しない。
(理由)200万円の修理・買い替え費用は、許容枠700万円の範囲内で支払うことが可能。あくまで「損失が大きい=入るべき」とは限らない。
④医療保険(保険料月5千円、入院給付日額1万円+手術給付金100万円)
- 加入しない。
(理由)仮に総額500万円の医療費がかかっても、公的保険と高額療養費制度の利用で、実質の自己負担は150万円程度に抑えられる。リスク許容範囲内。
⑤死亡保険(保険料月1,000円、保険金300万円)
- 加入しない。
(理由)死亡保険金には税制メリットがあるものの、300万円では遺族の生活維持には不十分。万一に備えるなら、必要保障額をカバーできる金額で加入すべき。中途半端な保障額であれば、むしろ運用に回した方が効率的。
⑥団体信用生命保険(保障料は借入金利に含む、住宅ローン残高5,000万円に)
- 加入する。
(理由)万が一の死亡時に住宅ローンが免除されない場合、遺された家族が住まいを失うリスクがある。これは明確に“許容できないリスク”であり、保険の本来的な意義に合致する。なお、団信は住宅ローンに付加されていることが一般的。
よくある疑問
- 保険に入った方が得することもあるのでは?
-
たとえば、車両保険に加入していて、実際に事故で数十万円の修理費がかかった——そんなときに保険で補償されれば、「やっぱり入っていて良かった!」と思うかもしれません。
ですが、それは“結果論”にすぎません。
保険は、そもそも多くの人が保険料を出し合い、その中から事故が起きた人にお金を支払う仕組みです。保険会社は、事故の確率や統計に基づいて保険料を設計し、そこに人件費・手数料・利益も上乗せしています。
この構造の中で、保険に「入った方が得する」ことが長期的に多発することはありません。保険を“得か損か”で考えると、本来の意義を見失い、投資や投機と似た視点になってしまいます。投資や投機をするのであれば、むしろ株式や投資信託などの金融商品の方が適しています。
- 元本保証タイプや貯蓄保険なら損しないのでは?
-
「貯蓄型保険」や「元本保証の終身保険」など、将来的に保険料が“戻ってくる”タイプの保険もあります。一見すると「これなら損はしない」と思えるかもしれません。
ですが、こうした保険商品にも見えにくいコストがいくつも存在します。
たとえば:
- 保険会社や販売代理店に支払われる高額な手数料(保険料の数%水準)
- 保険会社の運用コストや利益分が差し引かれている
- 早期解約では元本割れリスクも
保険会社は集めた保険料を資産運用にまわし、その運用益の一部だけが私たちに“還元”される構造となっています。自分で投資信託などを活用すれば、もっと効率よくお金を増やせた可能性もあります。
まとめ
保険は、「得をするかどうか」(損得勘定)で選ぶものではありません。
あなたがそのリスクを許容できるかどうか、これが保険選びのシンプルな判断軸です。
そのリスクをどう捉えるかを決めるのは、保険会社や営業担当ではなく、あなた自身です。
もちろん、保険の種類はますます複雑になっています。貯蓄型、外貨建、相続・生前贈与対策、健康増進型…挙げればキリがありません。
それでも、今回お伝えした考え方は、どんな保険商品にも共通する“判断のものさし”になるはずです。
- このリスクは、自分で背負えるか?
- 背負えないなら、どの保険が本当に必要か?
このような視点で選べば、もう不要な保険に振り回されることはなくなるでしょう。
リクルートが運営する「保険チャンネル」
他の記事もチェック