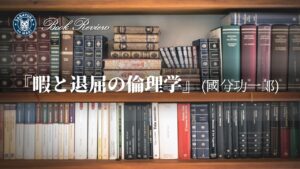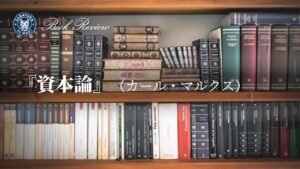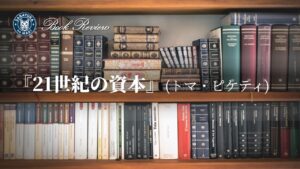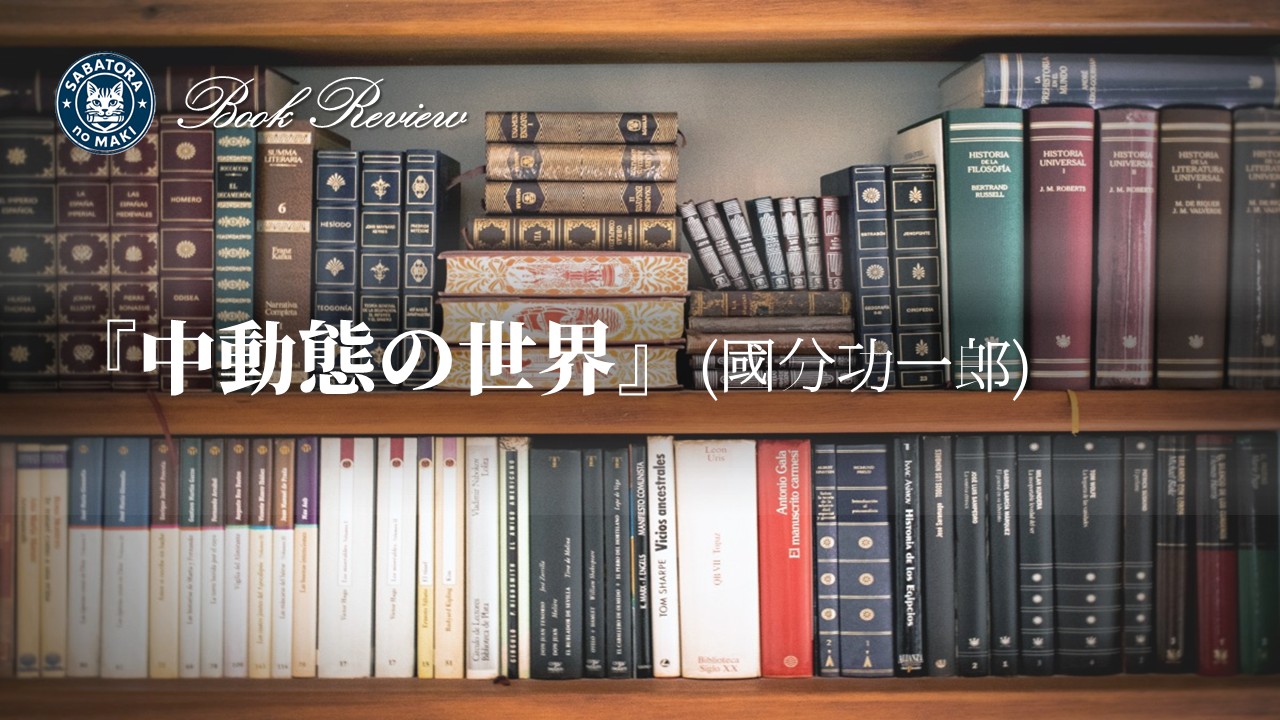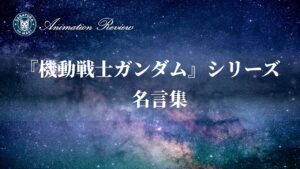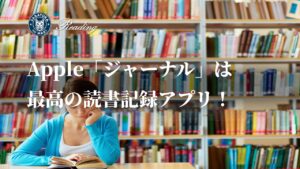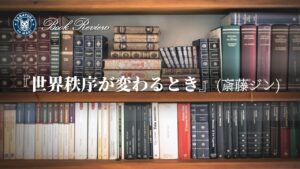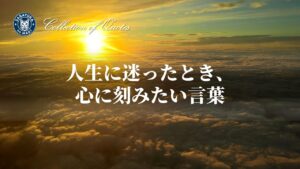「強い意志さえあれば、何でも乗り越えられる」
「失敗するのは、意志が弱いからだ」
——そんな言葉を、私たちは日常で耳にします。
そして、この「意志」の裏には、常に「責任」という重たい言葉が張りついています。
けれど、この「意志」は本当に、私たちが“自分で決めた”と言い切れるものなのでしょうか?
國分功一郎氏の『中動態の世界』は、その問いを深く掘り下げていく一冊です。
本書の冒頭で紹介されるのは、アルコール依存症の当事者による「酒もクスリも、自分の意志ややる気ではどうにもならない病気だ」という切実な言葉。そして、自傷行為に至った人が語る「自分で切ったのか、切らされたのかわからない」という告白。これらの言葉は、「意志の強さによって困難を克服できる」といった通念が、現実に存在する苦しみや背景の複雑さを捉えきれていないことを如実に物語っています。
哲学界の枠を超えて大きな反響を呼んだ本書は、第16回小林秀雄賞・紀伊國屋じんぶん大賞を受賞。2025年には補論を加えた文庫版が刊行され、再び注目を集めています。
この記事では、本書を読んで印象に残ったポイントや、そこから感じたことを、わかりやすく、丁寧にご紹介します。
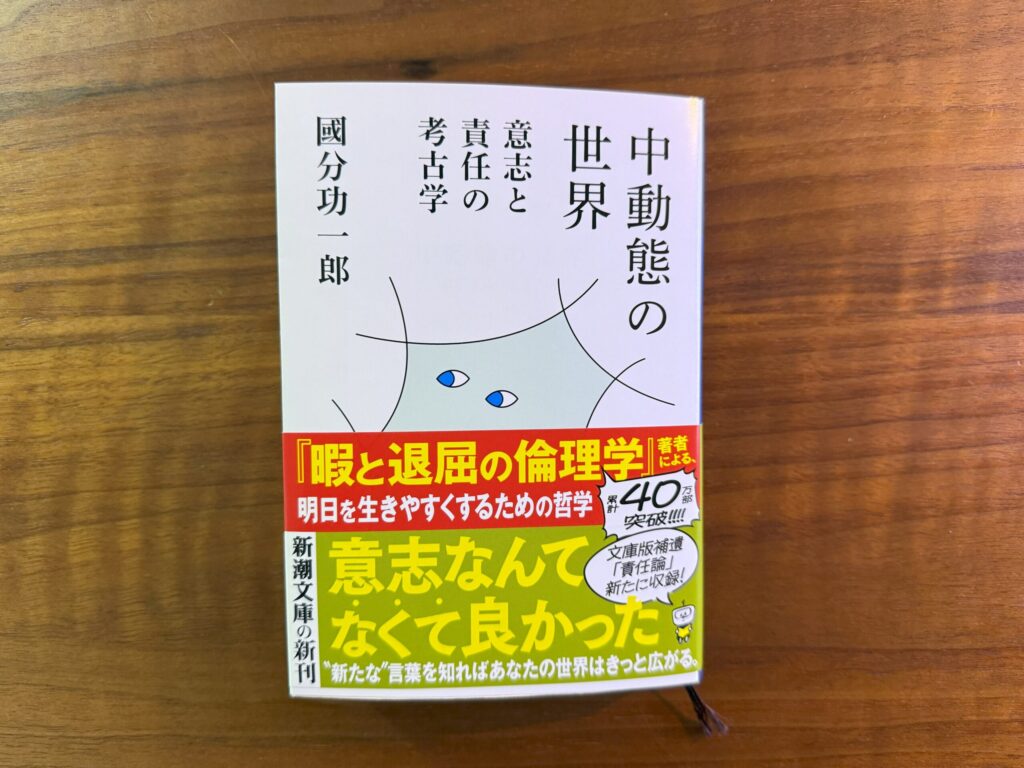
本書の主なポイント
本書を読んで感じたことを、筆者なりにかみ砕いてポイントを説明します。
「中動態」とは何か?
本書の中心概念である「中動態」とは、能動態(自分が意図的に行う行為)とも受動態(他者にされる行為)とも異なる、第三の動詞のあり方です。
例えば古代ギリシャ語では、「恋に落ちる」「涙があふれる」といった動詞は中動態で表されます。こうした感情や状態は、自分の意志で意図的に行うことでも、他者から強制されて行われることでもありません。あくまで「気がつけば自然と起きている」という、自分の内側で起こる動きを表現しています。
古代ギリシャ語では能動態は「殴る」「探す」など、他者に向けて働きかける行為に限定されていました。つまり、もともと行為は「自分の内側で完結するもの(中動態)」と「他者に向けられるもの(能動態)」の二つに分かれており、現代で馴染みのある受動態は、中動態から後に派生したものでした。
著者は、この中動態が歴史的に消失したことで、私たちが行為を「能動か受動か」という単純な二項対立でしか考えられなくなり、そこから「意志」という概念が生まれたと指摘します。
「意志」と「選択」の違い
私たちは普段、「意志」と「選択」を無自覚に混同しています。しかし、著者はこの二つを明確に区別します。
「意志」とは実は非常に暴力的な性質をもっています。なぜならそれは「過去の状況や条件を無視して、未来を一方的に決定する」からです。例えば、「明日から新しい自分になる!」と意志することは、「昨日までの自分」を否定して切り捨てる暴力性をはらんでいます。
“意志は実は曖昧さを抱えた概念であり、実際、最新の脳神経科学は行為の原動力としてのその役割を否定しつつある” ― 國分功一郎『中動態の世界』(新潮文庫、2025年)p.34
一方、「選択」とは、経済状況や社会的な圧力など、様々な外的要因によって「選ばされる」面が強くあります。例えば、「進学する大学や就職先を選ぶ」という場面でも、実際は家族や社会的期待、経済状況などの影響で「自由な選択」とは言い切れません。
“こう考えると、選択と意志の区別は明確であり、実に単純であると言わねばならない。望むと望まざるにかかわらず、選択は不断に行われている。意志は後からやってきてその選択に取り憑く。” ― 國分功一郎『中動態の世界』(新潮文庫、2025年)p.183
依存症や引きこもりなどの問題を「本人の意志が弱いから」と断定するのは、こうした複雑な現実を見落としています。
著者は日常的な「歩く」という動作を例に挙げ、「私たちは完全に意志で歩いているのではなく、むしろ『歩行という動作が自分の身体で自然に起こっている』と表現したほうが現実に近い」と述べます。
行為は「方向」ではなく「質」で決まる
では、能動と受動はどのように決まるのでしょうか。
著者は哲学者スピノザの考えを引きながら、行為は「誰が誰に向かって行うか」という「方向」ではなく、その行為が「どれだけ自分の本質に沿っているか」という「質」で考えるべきだと主張します。
“一般に能動と受動は行為の方向として考えられている。行為の矢印が自分から発していれば能動であり、行為の矢印が自分に向いていれば受動だというのがその一般的なイメージであろう。それに対しスピノザは、能動と受動を、方向ではなく質の差として考えた。” ― 國分功一郎『中動態の世界』(新潮文庫、2025年)p.359
例えば、カツアゲ(恐喝)で脅されて財布を差し出すという行為は、一見すると「強制された受動的行為」に見えます。けれども、「差し出すか否か」という選択肢がある中で、最終的に自ら手を動かして差し出しているという点では、どこか能動的な側面も否定できません。
しかし、スピノザ的な視点からすれば、この行為は「自分の本質が抑圧された状況で生じた」ため、質的に見て受動的な行為といえます。
このように、私たちの行為は単純に「する/される」といった二項対立では捉えきれません。だからこそ、中動態という第三の視点が必要になるのです。それは、複雑な現実をありのままに理解しようとするための枠組みなのです。
「中動態」で見る人間の深層心理と歴史
著者は、人間の感情にも「中動態的な本質」があると指摘します。特に注目するのが、「ねたみ」という感情です。
本書では、アメリカの作家ハーマン・メルヴィルによる小説『ビリー・バッド』が引用されます。ここで描かれるのは、ある種のねたみによって人が破滅へと向かうプロセスです。
「ねたみ」とは、他人と自分を比較することで、自分の価値が脅かされると感じる感情です。特に、「かつて自分がなりたかった理想像」を他者の中に見いだしたときに、その存在を否定したくなる——そうした心理が物語を通して描かれます。
主人公ビリー・バッドは、純粋さと美しさを兼ね備えた人物。彼の存在は、同僚クレッグの内面に潜んでいた「ねたみ」を呼び起こし、やがて破滅的な結末を導きます。
このような「ねたみ」は、単なる能動的な攻撃(たとえば嫉妬による加害)や受動的な自己否定とは異なります。それは、「自分でそう思ったのか、それとも外的なものにそう思わされたのか」が曖昧な、まさに中動態的な情動です。
能動でも受動でもなく、内と外の境界が溶け合うようなこうした感情は、まさに本書が示す「中動態的現象」の一つといえるでしょう。
また、マルクスは「人間は自らの歴史をつくるが、それを自らの自由な意志でつくるのではなく、与えられた状況の中でつくる」と指摘しました。私たちは自由に選択しているようでいて、実際には外的な制約や条件の中で「選ばされている」のです。
“歴史は人間が思ったようにつくり上げたものではない。だが、それは人間がつくった歴史と見なされる。ここにこそ、歴史と人間の残酷な関係がある。” ― 國分功一郎『中動態の世界』(新潮文庫、2025年)p.400
本書を読んで感じたこと
「自分の意志で決めた」は本当か?
本書を読んで、特に深く印象に残ったのは、「意志」や「責任」といった、私たちが日々の生活の中でごく自然に受け入れている考えが、実はそう単純には語れないものである——という視点でした。
私たちはふだん、「自分で決めた」と思って行動しています。進学、就職、転職、結婚、あるいは日々のライフスタイルの選択まで——それらの多くを、自分の自由な意志に基づくものだと疑うことなく受け止めているのではないでしょうか。
けれど、その選択は本当に「自分の意志」だけで行われたと言えるのか。思い返してみると、家族や世間の目、経済的な条件や周囲の期待といった「外からの力」によって、選ばざるを得なかった側面があったのではないか——そんなふうに、自分自身の経験とも重ねながら、静かに問いかけられるような読書体験でした。
小さな“ずれ”の感覚を見逃さない
本書を通じて、私はスピノザの「コナトゥス(自己保存の力/生きようとする力)」という概念にも、強く心を動かされました。
私たちはときに、「なんだかしんどい」「何かが違う」といった小さな“ずれ”を感じることがあります。それは、無理に自分を押し込めながら日常を生きているサインかもしれません。本来やりたくないことをしているとき、その違和感は、「自分の本質から離れてしまっている」というメッセージとして現れているのです。
たとえば、周囲の期待や社会の規範に自分を合わせ続けていれば、コナトゥス――つまり“その人らしさ”や“自然なあり方”は次第に抑え込まれ、生きる力が発揮されにくくなってしまいます。
「本質を生きる」とは、単に“好きなことだけをやる”ということではありません。むしろ、日々のささいな違和感や「なんとなくイヤだな」という感情に丁寧に耳を傾け、自分の中にある「本当の声」をすくい上げていくこと。著者は、その繊細な営みこそが、「自分らしく生きる」ための確かな手がかりになると語りかけてくれます。
中動態がもたらす希望
著者は、「ねたみ」「堕落」「自己否定」といった、一見ネガティブに見える感情や状態でさえも、中動態の視点から捉え直すことで、そこに希望の余地が見出せることを示唆しています。
たとえば、「人の成功を素直に喜べない」「自分に自信が持てない」といった感情に対して、私たちはつい「自分はダメだ」と結論づけ、自己評価を下げてしまいがちです。しかしそれは、「あなたが弱いから」と断じるべきものではありません。むしろ――「あなたの本質と、外部の環境や期待がぶつかって生じている現象」として捉え直すことができるのではないか。本書は、そうした視点の転換をそっと促してくれます。
「完全な能動も、完全な受動も存在しない」という前提に立てば、どれほど行き詰まっているように見える状況でも、そこには変化の余地が残されている。——この静かで、深く、力強い希望を与えてくれる視点こそが、中動態のもつ大きな可能性なのではないでしょうか。
“完全に自由になれないということは、完全に強制された状態にも陥らないということである。中動態の世界を生きるということはおそらくそういうことだ。われわれは中動態を生きており、ときおり、自由に近づき、ときおり、強制に近づく。” ― 國分功一郎『中動態の世界』(新潮文庫、2025年)p.411
まとめ
『中動態の世界』が教えてくれること——
それは、「能動か受動か」という単純な枠組みでは捉えきれない、第三の視点=中動態という世界の存在です。
この視点に触れるだけでも、私たちが「当たり前」と信じてきた“意志”や“責任”の意味が、大きく揺さぶられます。
人生の選択、感情の揺れ、人間関係のすれ違い——
そうしたすべてが、「自己責任」や「努力不足」といった物語では語り尽くせないことに気づかされるはずです。
こうした現実と誠実に向き合うために大切なのは、「この行動は本当に自分の本質に沿っているだろうか?」と問い続ける姿勢です。
問い続けることを通じて、私たちは少しずつ、社会や環境に振り回されることなく、自分の内なる本質に気づき、それを大切に生きる自由へと近づいていけるのではないでしょうか。