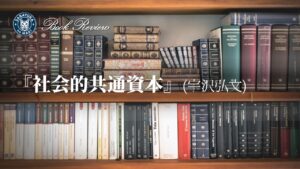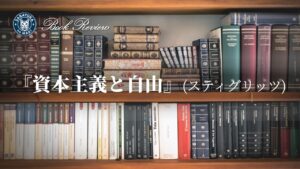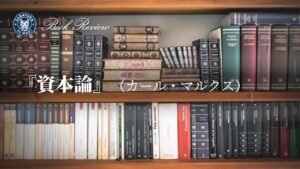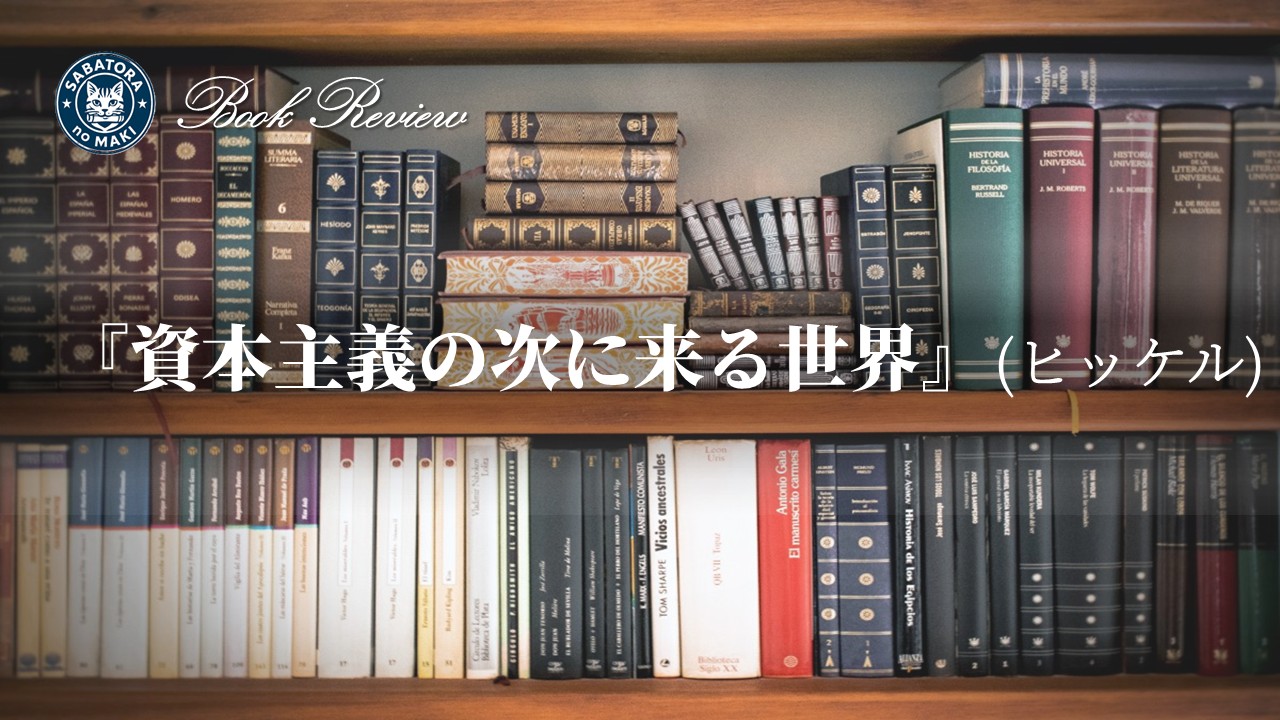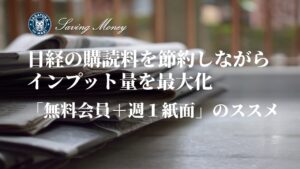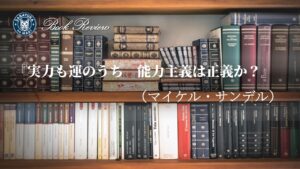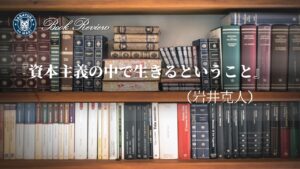現代社会では気候危機や格差拡大など、資本主義のもたらす副作用に多くの人が不安を抱き始めています。
ジェイソン・ヒッケル著『資本主義の次に来る世界』は、その原因を資本主義そのものに求め、徹底的な分析と大胆な提言を行う一冊です。
本書は「なぜ資本主義は誕生し、なぜ終わりが近いのか?」という歴史的視点から、「資本主義の構造的問題は何か?」「では資本主義の次にはどんな社会があり得るのか?」までを網羅し、読み手の想像力を大いに刺激してくれます。
単なる悲観論ではなく、持続可能で公正な未来への具体的なビジョンが描かれており、「脱成長(デグロース)」というキーワードにピンと来ない方にも希望を感じさせる内容となっています。

こんな人におすすめ
- 資本主義の仕組みに漠然とした疑問や違和感を抱いている人
- 経済格差や気候変動など持続可能性の危機に関心・危機感を持つ人
- 「脱成長」やポスト資本主義といった新しい経済モデルに興味がある人
- 豊かさとは何か、本当の幸福とは何かを見つめ直したい人
著者|ジェイソン・ヒッケルとは?
ジェイソン・ヒッケル(Jason Hickel)は、1982年生まれの経済人類学者です。
エスワティニ(旧スワジランド)出身で、ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス(LSE)などで教鞭を執り、グローバルな不平等やエコロジー経済学を専門としています。
また、脱成長論の旗手として知られ、無限の経済成長を前提とする現行の資本主義に異議を唱える研究者の一人です。本書『資本主義の次に来る世界(原題:Less is More)』では、そのヒッケル氏が提唱する「脱成長」思想のエッセンスが余すところなく語られています。
資本主義の問題点
本書は大きく二部構成になっています。
第1部「多いほうが貧しい」では、資本主義の歴史と問題点を掘り下げます。
ヒッケルはまず資本主義誕生の物語を振り返り、その舞台裏にあった流血の歴史を明かしています。たとえば、封建社会を覆した囲い込み(エンクロージャー)によって共有地(コモンズ)が私有化され、平等主義的だった共同体が崩壊させられた過程や、欧米による植民地化がいかに経済「成長」を加速させたかといった指摘です。近代の思想面にもメスを入れており、デカルト的な二元論(人間と自然の分離)が自然や人体を「征服すべき資源」とみなす発想を生み、資本主義の土台を支えたと論じています。
続いて、資本主義の内部論理としての成長至上主義に焦点が当てられます。ヒッケルは資本蓄積の原理を「ジャガノート(圧倒的破壊力)になぞらえ、資本は常にさらなる成長先を追い求めて突き進む」と表現します。企業は投資家の要求に応えるため、人工的に新たなニーズを生み出し、製品の寿命を意図的に短く(計画的陳腐化)することで消費を煽ります。その結果、私たちは「常に満たされない」状態に置かれ、際限ない消費サイクルに組み込まれてしまうのです。
資本主義の次に来る社会とは?
第2部「少ないほうが豊か」では、一転して希望に満ちた未来像が描かれます。
ヒッケルはまず「豊かな人生に本当に必要なものは何か?」という根源的問いを立て、経済成長と人間の幸福の関係をデータから問い直します。興味深いことに、アメリカでは人々が最も幸福だったのは1950年代であり、日本でも高度成長期を終えた1980年代のほうが現在より幸福度が高かったと本書は指摘します。
GDPが積み上がっても、社会全体の幸福には繋がらず、ごく一部の富裕層がさらに富む現実があります。だからこそ著者は、「医療や教育など基本的なニーズが行き渡った先進国では、むしろ経済規模を縮小したほうが人々は幸せになれる」と断言するのです。ここには、「成長=進歩」という従来の常識への痛烈な疑問が投げかけられています。
では、資本主義の次に来る社会を具体的に描くとしたら、どのような姿になるのでしょうか。
大量消費を止める
ヒッケルは、ポスト資本主義への道筋をいくつかのステップに分けて提示します。その象徴が「大量消費を止める5つの非常ブレーキ」という提言です。たとえば第一のブレーキは「計画的陳腐化を終わらせること」。スマートフォンをはじめ多くの製品で、意図的に寿命が短くなる設計がなされ、まだ使えるのに買い替えさせられる現状を是正しようというわけです。これは単に消費者の出費を減らすだけでなく、廃棄物削減や環境負荷の軽減にも直結する重要な施策です。
他にも「広告の規制によって不必要な欲望の煽動を減らす」「所有から利用への経済へ転換する(シェアリングエコノミーの推進)」「大量の食品廃棄を終わらせる」「化石燃料など生態系を破壊する産業の段階的縮小」といった具体策が示されています。ヒッケルの提案はどれも実行可能性のある現実的なものばかりですが、それらを徹底すればGDP(国内総生産)は縮小し、旧来的な意味での“経済成長”は止まってしまいます。そうなれば雇用への影響も避けられませんが、その点について著者はしっかり対策を用意しています。つまり「生産を減らす分、みんなで労働時間を短くシェアすればいい」というのです。経済がどれだけ成長しても労働時間はなかなか減らず、むしろ現代では高齢者も女性も働き詰めになっている。しかし不必要な経済活動を削減すれば、一人ひとりが取り戻せる「自由な時間」は飛躍的に増える——ヒッケルはそのようなポスト資本主義社会像を提示し、それは決して暗い停滞ではなく、明るい未来なのだと強調しています。
アニミズム的なものの見方
第2部の最後では、単なる政策論を超えて私たちの世界観の転換について論じられます。ヒッケルが鍵として挙げるのが先住民的な知恵やアニミズム的なものの見方です。近代以降の私たちは「人間 vs 自然」という二分法に囚われてきましたが、著者は「すべてはつながっている(Chapter6の章題)」という視点に立ち戻り、人間も生態系の一部として共生関係を結び直す倫理を提唱します。ここでは17世紀の哲学者スピノザの思想にも光が当てられ、デカルト的世界観の敗北とスピノザ的世界観の勝利という形で、新たな文明論が語られるのも本書のユニークな点です。
「少ないほうが豊か」——物質的な所有や消費を減らしても、むしろそのほうが人間も地球も豊かになれるという逆説的な発想ですが、本書を読み終える頃にはそのメッセージが不思議な説得力をもって心に残ることでしょう。
本書を読んでみて感じたこと
本書で指摘している資本主義システムの最大の特徴は、自己増殖的な性質です。
ヒッケルは資本主義を「際限のない指数関数的成長を信仰する宗教的なシステム」であると断じています。この表現は刺激的ですが、確かに資本主義のもとでは経済成長それ自体が目的化し、「とにかくGDPを増やせ」という圧力が政治・社会の隅々にまで染み渡っています。
しかしその一方で、私たち一人ひとりの実感としては、「なぜこんなにモノやサービスが溢れているのに満たされないのか?」「成長しているはずの経済の中で、なぜ将来不安が消えないのか?」という疑問が消えません。ヒッケルの指摘によれば、それこそ資本主義の巧妙な罠だということです。企業は利益を上げ続けるために人々の「欲望を決して満たさないこと」を目的に据えています。新商品や広告によって常に新たな欲求を植え付け、手に入れてもすぐ次の消費を促す──そうしなければ成長が止まり、資本主義が回らなくなるからです。これは裏を返せば、「人々の基本的なニーズが満たされ、皆が足るを知ってしまったら困る」という倒錯した論理でもあります。私たちが日々感じる漠然とした欠乏感や競争圧力は、実は構造的に作り出されたものなのかもしれません。
本書を読むと、資本主義下で当たり前と思っていた価値観を根底から揺さぶられる思いがしました。
資本主義のもう一つの構造的問題は、環境と社会への外部不経済を際限なく生み出すことです。
経済学で言う「外部化」とは、費用や負担を市場の外に押し付けることですが、資本主義はまさにそれを地球規模で行ってきました。大量生産・大量消費の裏側で、汚染された空気や水、気候変動による災害リスクといったツケが回ってきているのは周知の通りです。また、企業が効率を追求するあまり人件費を削減し、労働者を使い捨てにする傾向も深刻です。行き過ぎた市場原理が医療・教育など本来公共性の高い領域にまで及ぶと、弱者切り捨てや格差の再生産が進んでしまいます。ヒッケルが強調するように、資本主義は「富める者が信じられないほどのエネルギーを浪費する一方で、貧しい者には必要最低限さえ行き渡らない」という極端な不公平を内包しています。その非人間的な側面に、多くの人が薄々気づき始めているのではないでしょうか。
そして、資本主義の代替案として著者が提唱する「脱成長(デグロース)」。
一言で言えば、経済の目的を「人間と生態系の幸福」に据え直すことです。成長を自己目的化するのではなく、人々の生活向上を第一目標とし、その過程で必要であれば成長してもよいし、場合によっては縮小も厭わない——極めてシンプルですが、真っ当な価値転換です。決して「成長しない=貧しく停滞する」という意味ではなく、むしろ「本物の豊かさ」を実現するための経済モデルだという点が重要です。
このような脱成長の思想は、何もヒッケル一人が唱えているわけではありません。日本でも、経済学者の斎藤幸平氏が『人新世の「資本論」』などで資本主義の限界と脱成長コミュニズムを論じ、大きな注目を集めました。また宇沢弘文氏の「社会的共通資本」の議論(教育・医療・環境などみんなで守るべき価値を重視する考え方)とも通じるものがあります。ヒッケルの提示するビジョンには、こうした先行する議論とも響き合う普遍性があり、まさに資本主義の先を考える上で格好の出発点となるでしょう。
まとめ
『資本主義の次に来る世界』は、資本主義というシステムの本質と限界を正面から見据え、私たちに大胆な発想の転換を促す一冊です。
努力すれば報われ豊かになれると信じられてきた成長神話の裏に、実は深刻な不平等や環境破壊が潜んでいる現実を、本書は明快に示してくれます。ヒッケルが提案する脱成長社会は、「我慢」を強いるディストピアではなく、むしろ一人ひとりが人生の主役として真に豊かさを実感できる社会です。本書を読めば、従来の常識にとらわれない発想で「豊かさ」を再定義することが可能だとわかるでしょう。
本書のメッセージを要約すれば、「経済とは何のためにあるのか?」「私たちは何を共有し、何を守るべきか?」という根源的な問いかけに尽きます。資本主義の次に来る世界を考えることは、これらの問いに真正面から向き合うことでもあります。格差や気候変動といった難題に直面する今こそ、本書を手に取って資本主義の“その先”に思いを巡らせてみてはいかがでしょうか。きっと、これまで曇って見えていた未来に一筋の光が差し込み、私たち自身の生き方を見直すヒントが得られるはずです。
『資本主義の次に来る世界』は、そんな前向きな気づきと行動へのインスピレーションを与えてくれる必読の一冊だと感じました。