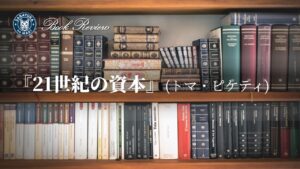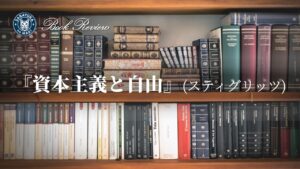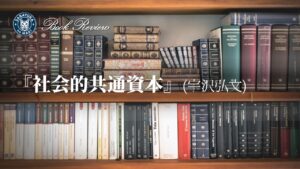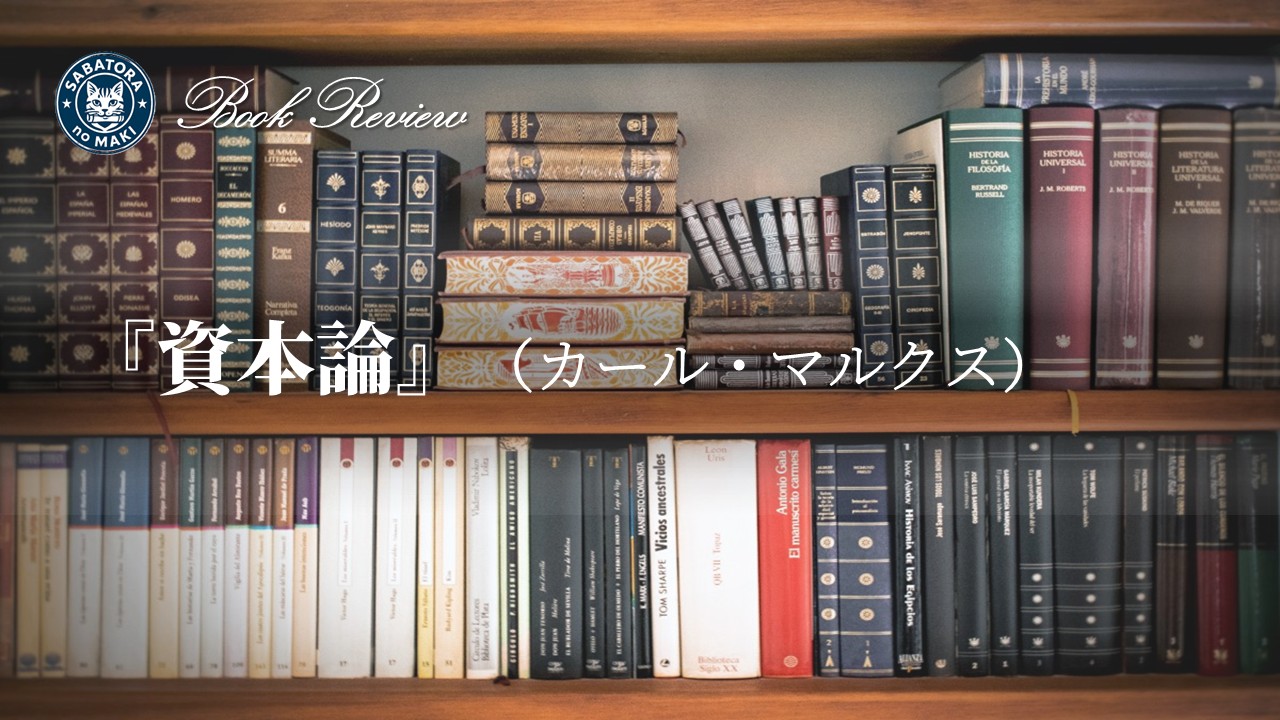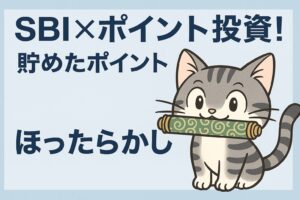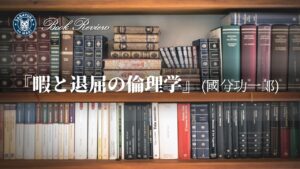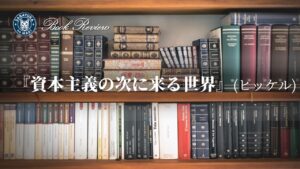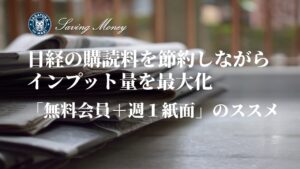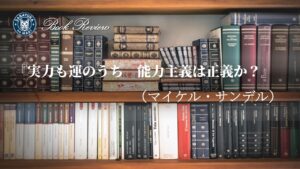現代社会の構造をより深く理解しようとするなら、マルクスの『資本論』は一度は触れておきたい一冊です。
「名前は聞いたことあるけど、難しそう」「共産主義と関係あるんでしょ?」という方も多いと思います。
この記事では、マルクスをほとんど理解していなかった筆者が、『資本論』を読んでポイントだと思った点や感じたことを、わかりやすくまとめます。
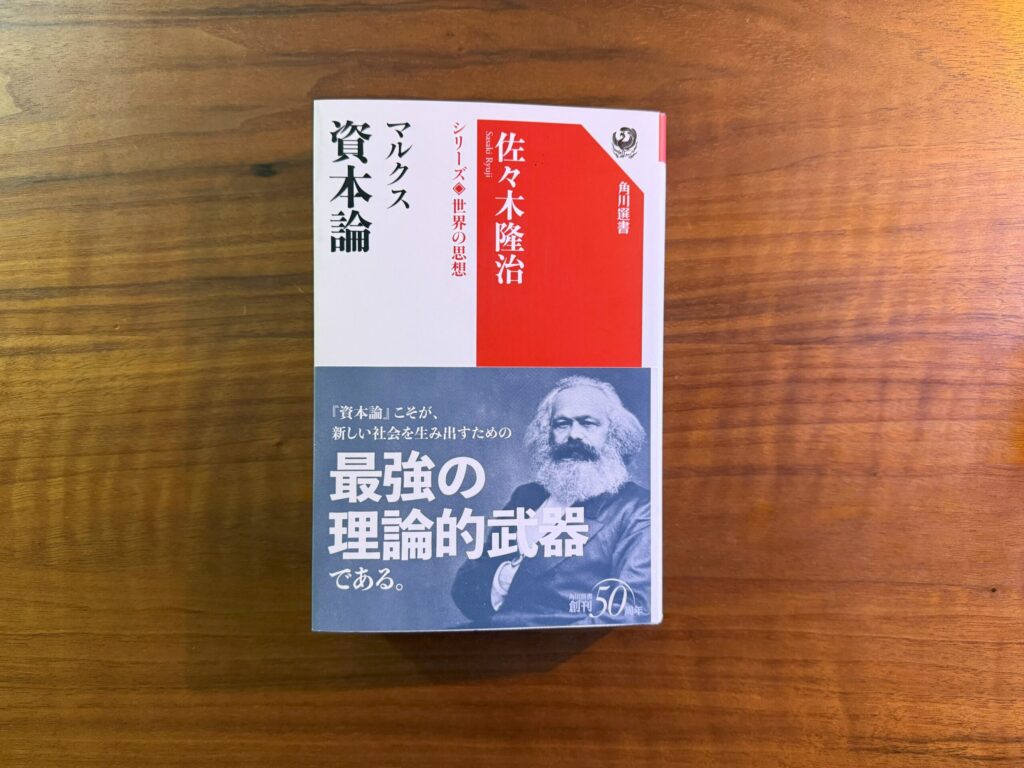
本を読む前のマルクスに対するイメージ
大学受験のときに、世界史で学んだ程度の筆者のマルクスに対するイメージは、以下のようなレベル。
エンゲルスとともに資本主義を批判し、共産主義という理想社会を提唱した人物。共産主義国家(ソ連やキューバなど)は実現したが、多くは失敗し、結果的に資本主義が世界の主流となった。
そんな「過去の思想家」という印象しか持っていなかった筆者が、いま『資本論』を読もうと思ったのには理由があります。
なぜいま『資本論』を読もうと思ったか?
お金が絶対的な価値を持つとされる現代の資本主義社会。しかし、それで本当に幸せになれるのか――。
そんな問いを抱く人が増える中、近年、マルクスの思想があらためて注目を集めていると感じます。たとえば、斎藤幸平氏の『人新世の「資本論」』は、その再評価の流れを象徴する一冊として話題になりました。
また、ビジネス書や哲学書においても、マルクスの思想がたびたび引用される場面を目にします。その中では、マルクスが語った資本主義の問題点や社会の理想像について、実は多くの誤解が広まっているとも指摘されています。
マルクスの思想に賛同するかどうかは別として、現代の資本主義というシステムを深く理解するには、一度はしっかりと読んでおきたい——。そんな思いから、『資本論』を手に取りました。
選んだ書籍
原著の『資本論』(岩波文庫など)はとにかく分量が多く、難解で有名です。
原著にチャレンジしたい気持ちもあったものの、途中で挫折しそうだったので、マルクスの原文を紹介しつつ丁寧に解説してくれる入門書として、レビューでも評価が高かった、佐々木隆治著『マルクス 資本論』(角川選書)を選びました。
この本は、マルクス自身が完成させた第1巻を中心に、重要な原文を紹介しながらわかりやすく解説してくれます。マルクスの思想をできるだけ歪めることなく、丁寧に伝えている点が魅力です。
「〇分で分かるマルクスの資本論」や「漫画で理解 マルクスの資本論」といったような要約本は、マルクスの意図を正しく理解できない可能性があるため、避けることにしました。
『資本論』の主なポイント
『資本論』を読んで感じたことを、筆者なりにかみ砕いてポイントを説明します。正確ではない点もあるかもしれませんが、資本主義について考えるきっかけとして、気軽に読んでいただけたら嬉しいです。
資本主義の出発点は「商品」
マルクスは、資本主義という経済システムを、「商品」という単位から分析します。
資本主義では、「あらゆるものが商品になる」とマルクスは説きます。
ここでいう「商品」とは、単なる物ではなく、次の2つの価値を持つものです:
- 使用価値:人間の欲求を満たす能力(例:パンなら食べて満腹になる)
- 交換価値:他の商品と交換できる価値(例:パン1個=りんご2個)
そしてマルクスは、後者の交換価値(『資本論』では単に「価値」と呼ばれる)の源泉は「抽象的人間労働」、つまり社会的に必要な労働時間にあると説きます。
労働も「商品」である
マルクスの重要な主張のひとつが、「労働そのものも商品になる」という点です。つまり、人間が持つ「労働する力=労働力」も、資本主義社会では市場で売り買いされる対象になります。
そして、労働力を売ることで生活する人々──いわゆる「賃労働者(労働者階級)」が生まれます。
労働力は、他の商品と同じように“価値”を持ちますが、ここで大事なのは、商品の価値そのものが「労働」によって生み出されるということ。つまり、労働は商品の価値の源であり、同時に商品としても売買されるという2つの側面があります。
そして、「資本家が労働力を商品として買い取り、それを使ってさらに価値を生み出す」という仕組みが、後ほど紹介する“資本の自己増殖”へとつながっていきます。
貨幣の登場
商品の交換が増えると、AとBのような「物々交換」では不便になります。そこで登場するのが「貨幣」です。
貨幣の導入によって、たとえば「商品A → 貨幣 → 商品B」と、間接的な交換が可能になります。これにより、商品交換は飛躍的に効率化しました。
ここで重要なのは、資本主義社会では、貨幣そのものも「商品」と化し、どんな商品とも交換できる「一般的等価物」としての特殊な地位をもつことです。
本来、貨幣は交換の手段にすぎないはずですが、やがてそれ自体が“欲望の対象”として追い求められるようになります。これがマルクスの言う「物神崇拝(フェティシズム)」です。
「資本主義=お金が支配する世界」といった漠然としたイメージを、マルクスは的確に言語化しています。
資本の運動と剰余価値
「資本」とは、単にお金やモノのことではありません。マルクスは、資本を「自己を増殖する価値」と定義しました。つまり、「お金を使って、さらにお金を増やす」という運動──それこそが資本の本質です。
マルクスは、貨幣を使った交換の動きを次の2つに分類しています:
- W(商品)→ G(貨幣)→ W(商品)
:消費のための交換(例:魚を売ってパンを買う) - G(貨幣)→ W(商品)→ G’(増えた貨幣)
資本による自己増殖(例:100円投資して120円を得る)
後者の G→G’ の差額(G’−G)が、いわゆる「剰余価値」と呼ばれます。
剰余価値はどこから生まれるのか?
資本家は、労働者の「労働力」を商品として買い取り、それを使って商品を生産します。労働者はその対価として賃金を得ますが、それはあくまで一部であり、労働者が生み出した価値のすべてが支払われるわけではありません。
たとえば:
- 労働者が1日で100の価値を生む商品を作る
- しかし彼の賃金は60しか支払われない
- 残りの40が剰余価値となり、資本家の利益になる
資本家はこの「40の剰余価値」を使って再び労働力を買い取り、商品を生産し、さらに利益を得る──。このループが続くことで、資本は自己を増殖し続けていきます。
このように、労働力の商品化こそが、資本が自己増殖する仕組みの根幹となっているのです。
資本家による労働の搾取
分業と機械化が進むことで、労働者はより単純な作業に従事するようになります。自分で商品を作るスキルがなくなり、生活するためには労働力を売るしかない存在になります。
つまり、働けば働くほど、労働者は資本主義の仕組みに組み込まれ、抜け出すのが難しくなります。
この構造の中で、資本家と労働者は二極化し、格差は拡大していく──これは、現代の社会問題にも直結するテーマです。
そしてここで重要なのは、こうした構造が違法に行われるなものではないという点です。
資本家は「労働力」を市場で購入し、その対価として賃金を支払うという正当な取引を行っています。つまり、搾取はルールの中で合法的に行われているのです。
マルクスの考える資本主義の未来
マルクスは、ここまで見てきたような資本主義の構造がやがて限界を迎え、労働者階級の団結(プロレタリア革命)によって社会の転換が起こると考えました。
その先にあるのは、生産手段を共有する社会。つまり、「私有財産の廃止」や「階級の消滅」といった共産主義のビジョンです。
しかし現実には、この理想は多くの混乱や抑圧を伴い、歴史的に大きな失敗を経験することになります。
とはいえ、資本主義が抱える「格差の拡大」「労働者の疎外」といった問題は、いまもなお世界中で指摘され続けています。
マルクスが示したビジョンそのものが現実化しなかったとしても、マルクスが突きつけた“問題の本質”は、現代にも通じるところがあります。
『資本論』を読んで感じたこと
会社員=賃労働者という構造の理解
最も印象的だったのは、労働者が生み出す価値と、その対価として受け取る賃金の差についてです。
これは会社員に当てはめて考えると分かりやすいかもしれません。
会社員が日々の仕事で利益を生み出し、その一部が賃金として支払われる。そして残りの利益は、資本家(企業側)にとっての剰余価値となり、再投資などに回される。
私たちはこの構造の中に無意識に組み込まれていても、それを意識する機会はあまりありません。ですが、マルクスは150年以上も前に、この「資本主義の仕組み」を理論的に説明していました。
もちろん、当時と比べれば労働環境は改善され、最低賃金や労働法なども整備されてきました。しかし、構造的には今も似たロジックが生きていると感じます。
搾取という言葉は現代では強すぎるように思いますし、すべての賃労働が不公平だというわけではありません。しかし、こうした構造を知らずに働いていると、自分の置かれた立場や労働の意味を見失い、気づかぬうちに“搾取される側”として選択肢を奪われてしまう可能性もあります。
だからこそ、資本主義の仕組みや「労働の価値」を知ることは、働き方や生き方をより主体的に選ぶための第一歩になるのではないでしょうか。
ポスト資本主義を考えるきっかけ
マルクスを読むことで、私たちが生きる「資本主義」というゲームの構造やルールを一歩引いて、俯瞰して見つめ直す視点を得ることができました。
現代社会では、資本主義は“最も発展した社会形態”として疑いなく受け入れられがちです。しかし、資本主義にも当然ながら限界やひずみは存在します。
マルクスのすべての主張が現代に通用するわけではありません。ですが、「なぜ貧富の差が生まれるのか」「労働とは何なのか」、マルクスのこうした根本的な問題提起は、いまもなお色あせることなく生きています。
なお、マルクスが描いた「資本主義の矛盾」は、現代にどう引き継がれているのか?
トマ・ピケティの『21世紀の資本』では、格差と富の集中が進む構造を、膨大なデータをもとに読み解いています。
『21世紀の資本』のレビューはこちら
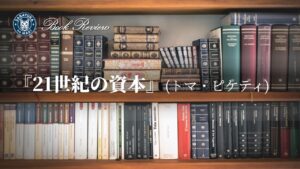
まとめ
資本主義の構造を理解するうえで、マルクスの『資本論』は外せない一冊です。
佐々木隆治先生の『マルクス 資本論』は、難解な原典に触れつつも、丁寧な解説で読みやすくまとめられており、初学者にもおすすめできます。
現代の働き方やお金との向き合い方に疑問を感じたとき、マルクスの視点は新たな気づきを与えてくれるはずです。